源平とその周辺:第5回 源頼朝の挙兵―山木攻めの勝利

 〈(山木)兼隆を討つ事は、来る十七日をその決行日と定められた。そこで、特に岡崎四郎義実・同与一義忠を頼りに思い、十七日以前に、土肥次郎実平と共に参上するよう、今日義実のもとに命を伝えられたという。〉『吾妻鏡』(引用文献 『現代語訳 吾妻鏡』五味文彦・本郷和人編 吉川弘文館)
〈(山木)兼隆を討つ事は、来る十七日をその決行日と定められた。そこで、特に岡崎四郎義実・同与一義忠を頼りに思い、十七日以前に、土肥次郎実平と共に参上するよう、今日義実のもとに命を伝えられたという。〉『吾妻鏡』(引用文献 『現代語訳 吾妻鏡』五味文彦・本郷和人編 吉川弘文館)
文覚、という僧がいた。彼がまだ出家前の遠藤盛遠であったとき、人妻の袈裟御前に懸想してその夫を殺そうとしたが誤って袈裟御前を殺害。以後、僧となって諸国を遍歴し、修行に励む。特に神護寺の復興に力を入れた。彼は後白河法皇の御所に押しかけて神護寺への荘園の寄進を強要するなどして、伊豆国へ流罪となった。伊豆には、頼朝がいた。文覚は頼朝の父義朝の髑髏を見せて平家を打倒するよう説得し、後白河法皇の院宣を得て頼朝に決起を促したと『平家物語』では伝える。
治承4年(1180)4月、頼朝の叔父の源行家によって以仁王の令旨が北条館にもたらされる。8月、頼朝がまず攻めようと決めたのは、平氏系の武士で伊豆の国の目代であった山木兼隆。冒頭の引用文では、山木攻めの決行日以前に頼朝のもとへ参上するよう、岡崎義実やその子与一に要請があったというもの。頼朝が旗揚げするにあたって頼みとしたのが、北条時政などの伊豆の武士や、岡崎氏や土屋氏をはじめとした相模の武士たちであった。
8月17日、三島社の神事の日。雨による川の増水で佐々木兄弟(定綱、経高、盛綱、高綱)が遅参したために、予定していた朝の合戦は見送られた。そして夜。兼隆の郎従たちの多くが三島社に参詣し、人が少なくなっていた山木の館を襲撃。万一の時のために北条の館に残っていた頼朝は、朝になってようやく合戦を終えて帰参した武士たちが持ってきた兼隆主従の首を確認した。頼朝挙兵の第一歩、深夜の山木攻めは成功した。
写真:源氏山公園内に建てられている『源頼朝公銅像』(鎌倉市扇ガ谷4丁目649‐1)
新村 衣里子
■プロフィール
お茶の水女子大学大学院博士前期課程修了。元平塚市市民アナウンサー。平成16年ふるさと歴史シンポジウム「虎女と曽我兄弟」でコーディネーターをつとめる。『大磯町史11別編ダイジェスト版おおいその歴史』では中世の一部を担当。成蹊大学非常勤講師。
 シェア
シェア
 シェア
シェア
 で送る
で送る
湘南ローカル情報を日々更新中!
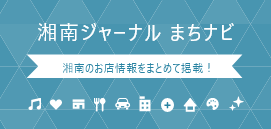
湘南のお店情報をまとめて掲載!
編集部情報を毎週更新でお届けします。
-
お知らせ|2023.12.14
2023-2024年 年末年始の休業のお知らせ
-
お知らせ|2023.09.18
WEBメディア・Journal ONEに弊社代表定成のインタビュ...




